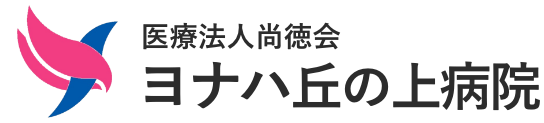旅するソーシャルワーカー✈の桑員歴史コラ...
広報ブログBlog
旅するソーシャルワーカー✈の桑員歴史コラム「丘の上から🍃」 第1回(歴史1)
長島藩に仕えた河合曽良、芭蕉と
『おくのほそ道』を往く
<壱岐の海に眠る曽良>
令和6年(2024)10月、壱岐島(長崎県壱岐市)を初めて訪ねました。風光明媚な観光の島で、特に勝本港から船で渡る辰ノ島はエメラルドグリーンの海が広がる絶景の島でした。実は、この勝本浦には意外にも桑名ゆかりの人物の墓があります。俳人松尾芭蕉(1644~1694)の門人で、長島藩に仕えた河合曽良(1649~1710)です。かつて勝本城があった城山の中腹にある能満寺(長崎県壱岐市勝本町坂本触)の墓地には、上部を欠いた曽良の墓があります。正面には「賢翁宗臣居士」と曽良の戒名が刻まれ、その傍らには壱岐市教育委員会による解説板が立ち、そこには曽良が長島で過ごしたことが書かれています。元長島藩士の曽良はどうして遠く離れた壱岐に眠っているのでしょうか。
<信濃諏訪から伊勢長島へ>
曽良は信濃国諏訪郡下桑原村(長野県諏訪市諏訪)で富裕な商家である高野七郎兵衛と母河西氏の長男として生まれましたが、早くに両親を亡くしたことから近隣に暮らす母方の伯母の夫岩波久右衛門昌秀の養子となって岩波庄右衛門正字(まさたか)を名乗りました。しかし、万治3年(1660)1月に養父、6月に養母と相次いで死別したことから、伯父で大智院(桑名市長島町西外面)の住職を務める深泉良成(?~1731)の許に身を寄せ、河合惣五郎と名乗って長島藩に仕えました。河合姓は母方河西家の祖先で武田家に仕えた河合美四良光連にちなむとも、長島藩士「川合」源右衛門長征の養子になったからとも言われます。
<木曽川と長良川から曽良を名乗る>
長島に来訪した時期については12歳の万治3年(1660)と19歳の寛文7年(1667)の説があります。また、長島藩を致仕して江戸に上った時期は延宝4年(1676)から天和3年(1683)の間とされることから、少なくとも9年間、長くて23年間を長島で過ごしたことになります。長島時代の曽良の事績を伝えるものは少なく、延宝4年(1676)に大智院で正月を迎え、曽良の号で「袂から春は出たり松葉銭」(「曽良歳旦吟」)の句を残しています。ただし、この句は郷里諏訪で詠まれたという説もあります。句の前には「朝より遠山のかすみ谷川のぬるみも有へきに八面一色の雪国に年をむかへ」たとあり、確かに長島では「雪国」といった表現に違和感があります。なお、曽良の名は長島を囲む木「曽」川と長「良」川にちなむと伝わります。
<芭蕉と『おくのほそ道』の旅へ>
長島を去った曽良は江戸へ上り、幕府神道方の吉川惟足(1616~1695)に師事して神道を学び、貞享2年(1685)頃になって深川に居を定めたところ、近くに住む芭蕉と出会って俳諧の教えを乞うようになりました。俳諧を通じて親交を深めた師弟は元禄2年(1689)3月27日に江戸を発ち、450里、155日間にわたる『おくのほそ道』の旅を始めます。現在の東京から埼玉、茨城、栃木、福島、宮城、岩手、山形、秋田、新潟、富山、石川、福井を経て岐阜に至る1都13県を巡る長い旅路で、終着点となった大垣市には奥の細道むすびの地記念館(岐阜県大垣市船町)があります。この旅において曽良が記した日記は、『奥の細道曽良随行日記』(天理大学附属天理図書館蔵)として昭和53年(1978)6月15日に国の重要文化財に指定されています。曽良は旅の終盤になって体調を崩し、8月5日に山中温泉(石川県加賀市)で芭蕉と別れ、先行して長島へ戻りました。『おくのほそ道』には「曽良は腹を病みて、伊勢の国長島と云ふ所にゆかりあれば、先立ちて行く」と記されています。曽良は大垣から船に乗り、8月15日になって長島に到着しています。芭蕉の長島到着は9月6日のことです。「予(曽良)、長禅寺へ上(あがり)て、陸をすぐに大智院へ到(いたる)」(『奥の細道曽良随行日記』)。
<壱岐で病没>
宝永7年(1710)、幕府より巡見使随員を命じられた曽良は5月7日に壱岐島に上陸するも、病を得て勝本浦の海産物問屋中藤家で看病を受け、対馬への渡航を断念します。しかし、快方には向かわず、5月22日に息を引き取りました。享年62歳。墓は中藤家の墓所である能満寺に建てられ、後に諏訪の正願寺(長野県諏訪市岡村)にも建立されました。壱岐の墓は平成16年(2004)3月1日に壱岐市指定記念物となっています。また、平成6年(1994)5月24日には、河合曽良の出身地諏訪市と終焉の地である勝本町(現在の壱岐市)が曽良を縁として友好都市提携を結び、合併後の壱岐市にも引き継がれて交流が続いています。
<参考:長崎県壱岐市の「俳人曽良の墓」解説板>
市指定記念物 俳人・曽良の墓
指定年月日 平成16年3月1日
【おいたち】
河合曽良は慶安2(1649)年に信州上諏訪〔現在の長野県諏訪市〕に生まれ、幼少期を過ごした。若い時に両親を亡くし、伯父がいる伊勢長島〔現在の三重県桑名市〕で成人し、伊勢長島藩主松平土佐守良尚、松平佐渡守忠充に仕官し、河合惣五郎として活躍した。
【松尾芭蕉との出会い】
松平家に仕官したのち、江戸に移り、神道家・吉川惟足に入門し国学を学んだ。その時に俳人・松尾芭蕉と出会い、弟子入りし木曽川と長良川に挟まれる長島の地にちなんで“曽良”の俳号を用いた。その後松尾芭蕉の代表作である『奥の細道』の旅にも同行し、数多くの俳歌を残している。また、『奥の細道』紀行中の記録を『曽良随行日記』として書き残しており、道中の足取りが鮮明に書かれていることから当時の芭蕉の動向を窺い知ることができる貴重な資料として昭和53(1978)年6月15日に国重要文化財に指定されている
【巡見使としての曽良】
曽良は仏門に入り、名も「宗悟」と改める。仏門の道を究めるも、『奥の細道』に同行した実績や国学においても知識が豊富であったことから、江戸幕府の巡見使に抜擢された。宝永6(1709)年に6代目将軍徳川家宣が将軍職に就任する際に巡見使視察の命が発令され、曽良は九州地方の実情の実見を担当することとなり、翌年に江戸を出発し豊前国から肥前国を見て廻ったのち佐賀の呼子を出発し、壱岐勝本浦に入港した。島内の巡見を行い、対馬に向かう予定であったが、体調を崩したため勝本の海産物問屋であった中藤家に残ったものの容態は悪化し、そのまま息を引き取った。死後、曽良の墓は中藤家の墓地内につくられ今日に至っている。
令和5年7月 壱岐市教育委員会
<参考文献>
- 岡本耕治『曽良長島日記 第二の故郷における足跡』岡本耕治1992
- 岡本耕治『曽良長島異聞 第二の故郷における謎』岡本耕治1995
- 穎原退蔵・尾形仂訳注『新版 おくのほそ道』角川書店 2003
- 金森敦子『「曽良旅日記」を読む もうひとつの「おくのほそ道」』法政大学出版局 2013

辰ノ島のエメラルドグリーンの海(長崎県壱岐市)

河合曽良の墓(長崎県壱岐市・能満寺)

蕉翁信宿処碑(桑名市長島町西外面・大智院)

大智院前の長良川(桑名市長島町西外面)

芭蕉門人曽良の像(山形県山県市・立石寺)

能満寺から眺めた勝本浦(長崎県壱岐市・能満寺)
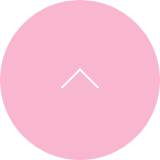
交通アクセスACCESS
お車でお越しの場合
-
高速道路をご利用の場合
東名阪自動車道桑名ICより東桑名市街方面 約5分
-
高速道路をご利用されない場合
国道23号線和泉ICより北西 約15分
国道258号線経由国道421号線沿い
電車・バス・タクシーでお越しの場合
- 近鉄・JR桑名駅より三重交通バス
- 近鉄・JR桑名駅よりタクシー約10分
- 桑名市コミュニティバス(K-バス)西部南ルート バス停希望ヶ丘より北西 徒歩約5分